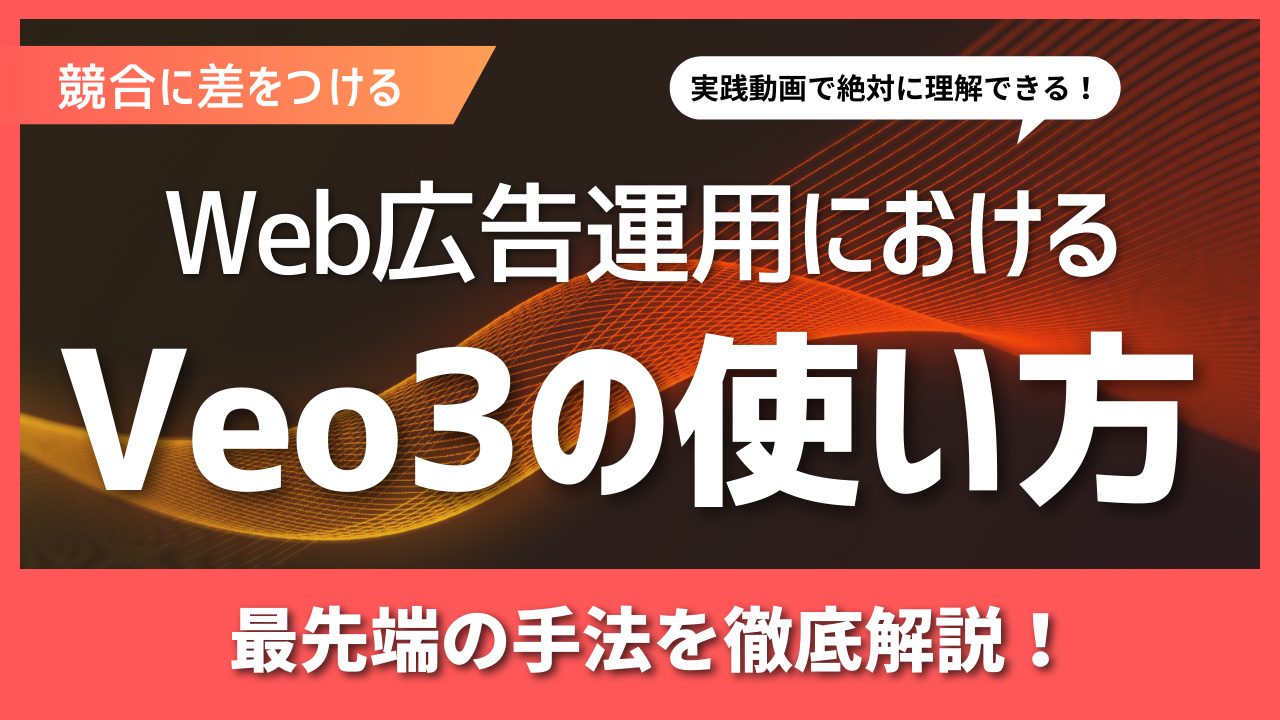記事
 2025.10.21
2025.10.21
 2025.10.21
2025.10.21
【2025年版】生成AI資格でおすすめランキング!試験難易度と選び方を解説

AI技術の進化が加速するなか、生成AIに関する資格を取得したいと考えている方も増えています。しかし、多くの資格が登場しているため、どれを選べばよいのか迷ってしまうことも多いでしょう。
本記事では、2025年時点でおすすめの生成AI資格をランキング形式でご紹介します!
おすすめランキングだけでなく、試験の難易度や選び方についても詳しく解説していきますので、これから資格取得を目指す方の参考になれば幸いです。
生成AI資格とは?
生成AI資格とは、ChatGPTやStable Diffusionといった生成AIツールの活用方法や、その背景にある技術を体系的に学び、理解していることを証明する資格です。近年のAIブームを受けて、企業や教育機関でも生成AIに関する知識が求められるようになり、資格の種類も急速に増えています。
そもそも生成AIとは何か?
生成AIとは、テキスト・画像・音声・動画などのコンテンツを自動的に生成する技術を指します。従来のAIが「データを分析して予測する」役割を担っていたのに対し、生成AIは「新しい価値を創造する」点が大きな特徴です。
生成AIの代表的なツール
たとえば、ChatGPTのような対話型AIは文章を生成し、Stable Diffusionのような画像生成AIはプロンプトをもとに絵を描き出します。こうした技術は、業務の効率化やクリエイティブな表現の幅を広げる手段として、さまざまな分野で活用されています。
資格取得の重要性
生成AI資格を取得する意義は、単にスキルを証明するだけにとどまりません。これからのビジネスシーンでは、AIを適切に使いこなす能力が競争力の源泉となります。
客観的なスキル証明
資格を持っていることで、転職や昇進の際にスキルを客観的に示せるだけでなく、社内でのAI導入プロジェクトにおいても説得力のある提案ができるようになります。
体系的な知識の習得
また、資格取得の過程で得られる体系的な知識は、実務での応用力を高める土台となります。AIツールを感覚的に使うだけでなく、仕組みやリスクを理解したうえで運用できる人材は、企業から高く評価される傾向にあります。
生成AI資格の種類と用途
生成AI資格には、初心者向けの基礎的なものから、エンジニア向けの高度な技術を扱うものまで、さまざまな種類が存在します。
ビジネス職向けの資格
ビジネス職や営業職の方が生成AIの基本的な活用法を学びたい場合は、生成AIパスポート試験のような入門レベルの資格が適しています。
エンジニア向けの資格
一方で、AI開発に携わるエンジニアやデータサイエンティストを目指す方には、E資格のような実装力を問う資格が有効です。
人気の生成AI資格ランキング
ここからは、2025年時点で特に注目されている生成AI資格を、初心者向け・国家資格・上級者向けの3つのカテゴリに分けてご紹介します。
初心者向けの生成AI資格
生成AIに初めて触れる方や、文系・非エンジニアの方でも挑戦しやすい資格として、以下の3つが挙げられます。
1位 Generative AI Test(GAT)
Generative AI Test(GAT) は、日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する試験で、生成AIの基本概念やリスク管理について問われます。受験料は2,200円と手頃で、合格率も60~70%程度と比較的高いため、最初の一歩として取り組みやすい資格です。
合格すると「オープンバッジ」が付与され、履歴書やSNSでスキルをアピールする際に役立ちます。試験時間は20分、オンライン形式で年2回実施されています。
2位 生成AIパスポート試験
生成AIパスポート試験は、一般社団法人GUGAが主催する資格で、生成AIの仕組みやリスクの基礎を学べます。受験料は一般11,000円、学生5,500円で、年3回実施されています。
合格率は約77%と高めで、合格者には合格証書とオープンバッジが発行されるため、社内でのAIリテラシーの証明や、転職活動でのアピール材料として活用できます。試験時間は60分で、オンライン形式で受験可能です。
3位 ITパスポート
ITパスポートは、国家資格として広く認知されており、IT全般の基礎知識を問う試験です。AIに特化しているわけではありませんが、情報処理やセキュリティの知識を含むため、生成AIを含むデジタル技術全般の基礎を固めたい方におすすめです。
受験料は7,500円で、全国のCBT会場で随時受験でき、合格率は約50%程度です。
上級者向け生成AI資格
すでにAIやプログラミングの知識を持ち、さらに高度なスキルを証明したい方には、以下の資格が適しています。
E資格(エンジニア資格)
E資格(エンジニア資格) は、JDLAが実施するディープラーニングの実装力を問う試験で、受験にはJDLA認定プログラムの修了が必須です。受験料は一般33,000円、学生22,000円で、年2回実施されています。
合格率は約68%とやや高めですが、高度な数学やPythonプログラミングの知識が求められるため、しっかりとした準備が必要です。合格すると、AIエンジニアとしての技術力を対外的に証明でき、転職や昇進の際に大きなアピールポイントになります。試験時間は120分で、CBT方式で実施されます。
G検定(ジェネラリスト検定)
G検定(ジェネラリスト検定) も、JDLAが主催する資格で、AIやディープラーニングの全体像を理解していることを証明します。受験料は一般13,200円、学生5,500円で、年6回実施されています。
合格率は約81%と高めですが、AIの歴史や法律など幅広い知識が問われるため、体系的な学習が求められます。マーケティングや戦略立案に関わる職種の方にとって、AIの全体像を把握するうえで有用な資格です。試験時間は120分で、オンライン形式で受験できます。
AWS Certified AI Practitioner(AIF)
AWS Certified AI Practitioner(AIF) は、Amazon Web Services(AWS)上での生成AI活用に関する基礎知識を問う資格で、受験料は16,500円です。クラウド環境でのAI運用を学びたい方や、リモートワークや副業での活用を考えている方におすすめです。試験時間は90分で、テストセンターまたはオンラインで受験可能です。
生成AI資格の試験難易度と合格率
生成AI資格を選ぶ際には、試験の難易度や合格率も重要な判断材料となります。
各資格の難易度を比較
生成AI資格の難易度は、受験資格の有無や出題内容、必要な前提知識によって大きく異なります。
初心者向け資格の難易度
Generative AI Test(GAT) や 生成AIパスポート試験は、受験資格が不要で初心者でも挑戦しやすい内容です。試験時間も短く、基礎的な知識が中心となるため、独学でも十分に対応できます。学習時間の目安は10~30時間程度です。
上級者向け資格の難易度
一方で、E資格はJDLA認定プログラムの修了が必須で、ディープラーニングの実装力が問われるため、難易度は高めです。Pythonや数学の知識が必要となり、100~300時間程度の学習時間が推奨されています。
中級資格の特徴
G検定は、E資格ほど高度な技術は求められませんが、AIの歴史や法律など幅広い分野から出題されるため、体系的な理解が必要です。学習時間の目安は30~50時間程度となります。
合格率の推移とその理由
生成AI資格の合格率は、資格の種類や試験の性質によって大きく異なります。
初心者向け資格の合格率
Generative AI Test(GAT) の合格率は約60~70%とされており、基礎的な内容が中心であることから、しっかりと学習すれば合格が狙える水準です。生成AIパスポート試験の合格率は約77%と高めで、初心者向けの設計となっています。
中級・上級資格の合格率
G検定の合格率は約81%と高い水準を維持していますが、これは試験範囲が広いものの、基本的な理解を問う内容が中心だからです。一方で、E資格の合格率は約68%とやや低めで、高度な技術力が求められるため、十分な準備が必要です。
試験対策のポイント
生成AI資格の試験対策では、効率的な学習方法を選ぶことが合格への近道です。
過去問・模擬試験の活用
まず、過去問や模擬試験を活用することが重要です。出題形式や頻出分野を把握することで、学習の優先順位をつけやすくなります。特に、G検定やE資格は過去問が公開されているため、繰り返し解くことで実力を高められます。
オンライン学習の活用
次に、オンライン講座やアプリを活用することで、隙間時間に効率よく学習できます。UdemyやスキルアップAIなどのプラットフォームでは、試験対策に特化した講座が提供されています。
コミュニティの活用
また、コミュニティや参考書を活用することで、疑問点を解消しやすくなります。SlackやDiscordのAI系グループに参加すれば、同じ目標を持つ仲間と情報交換ができ、モチベーションの維持にもつながります。
生成AI資格を活用するメリット
生成AI資格を取得することで得られるメリットは、単なる知識の習得にとどまりません。
キャリアアップに役立つ資格
生成AI資格を持っていることで、転職や昇進の際に大きなアピールポイントとなります。AI技術は今後もさまざまな業界で活用が進むため、生成AIに関する知識を持つ人材の需要は高まり続けています。
転職・昇進での優位性
たとえば、G検定やE資格を取得していれば、AIプロジェクトのリーダーやエンジニアとして評価されやすくなります。実際に、これらの資格を持っている方が、社内の新規プロジェクトに抜擢されたという事例も少なくありません。
社内でのポジション確立
また、履歴書や職務経歴書に資格を記載することで、面接時の話題作りや、他の候補者との差別化にもつながります。AIの導入や活用を推進する立場になることで、責任ある役割を担う機会が増え、キャリアの幅を広げることができます。
業務効率化における資格のメリット
生成AI資格を取得することで、実務での業務効率化に直結するスキルが身につきます。
実務での活用例
たとえば、生成AIパスポート試験やGenerative AI Test(GAT) で学ぶ内容は、ChatGPTやBingなどのツールを業務に活用する際の基礎となります。議事録の自動作成やメール文の迅速な生成、データ分析の補助など、日常業務のさまざまな場面で生成AIを活用できるようになります。
チーム全体への波及効果
業務効率化は、個人の生産性向上だけでなく、チーム全体のパフォーマンス向上にもつながります。生成AI資格を取得することで、こうした実務に直結するスキルを体系的に習得できる点は大きなメリットといえるでしょう。
フリーランスの活動にも有利
生成AI資格は、フリーランスや副業で活動する方にとっても大きな武器となります。
案件獲得での優位性
クラウドソーシングサイトやSNSでスキルをアピールする際、資格を持っていることで信頼性が高まり、案件を獲得しやすくなります。たとえば、G検定や画像生成AI能力検定を取得していれば、AIを活用したコンテンツ制作やデータ分析の案件で優遇されることがあります。
単価アップの可能性
また、資格を持っていることで、単価の高い案件にも挑戦しやすくなります。実際に、生成AI資格を取得したライターやデザイナーが、AIを活用した業務を前提とした案件を受注し、収入を増やした事例も報告されています。
生成AI資格の取得方法と学習リソース
生成AI資格を効率よく取得するには、自分に合った学習方法を選ぶことが重要です。
独学と講座の選び方
生成AI資格の学習方法には、独学と講座受講の2つの選択肢があります。
独学のメリットとデメリット
独学のメリットは、自分のペースで学習できることや、費用を抑えられることです。UdemyやYouTubeなどの無料・低価格の教材を活用すれば、コストをかけずに学習を進められます。一方で、独学では疑問点を解消しにくく、学習の方向性が定まりにくいという課題もあります。
講座受講のメリット
講座受講のメリットは、体系的なカリキュラムで学べることや、講師に質問できる環境が整っていることです。特に、E資格のようにJDLA認定プログラムの修了が必須の資格では、講座受講が前提となります。また、講座では最新の試験範囲に対応した内容が提供されるため、効率よく学習を進められます。
推奨教材とオンラインコースの紹介
生成AI資格の学習には、信頼性の高い教材やオンラインコースを選ぶことが重要です。
初心者向けの教材
Generative AI Test(GAT) や 生成AIパスポート試験については、公式サイトで推奨されている教材や過去問を活用するのが効果的です。また、Udemyでは「生成AI入門講座」や「ChatGPT活用術」といったコースが提供されており、初心者でもわかりやすい内容となっています。
G検定・E資格向けの教材
G検定やE資格については、JDLA公式の参考書や、スキルアップAIなどのオンラインプラットフォームで提供されている試験対策講座が有効です。特に、E資格の受験資格を満たすためには、JDLA認定プログラムの受講が必須となるため、認定講座の一覧を確認して、自分に合ったものを選びましょう。
受験資格についての詳細
生成AI資格の多くは、受験資格が不要で誰でも挑戦できるものが多いですが、一部の資格では特定の条件を満たす必要があります。
E資格の受験資格
E資格は、受験前にJDLA認定プログラムを修了していることが必須です。認定プログラムは、複数の企業や教育機関が提供しており、受講期間や費用はプログラムによって異なります。
受験資格不要の資格
ITパスポートやG検定、生成AIパスポート試験などは、受験資格が一切不要で、誰でも受験できます。初心者の方や、まずは基礎から学びたい方には、こうした資格から始めるのがおすすめです。
生成AI資格取得後のキャリアパス
生成AI資格を取得した後、どのようなキャリアを築いていけるのでしょうか。
今の仕事でスキル
一番現実的なのは今の仕事にてスキルアップをしたりすることなのではないでしょうか?今時間をかけて行っている仕事を効率化したり、社内でAIを布教したりと、今の職場であったり、ご自身の会社の業績アップに知識を活用することができます。
転職をする
新しい資格と知識を兼ね備えていることをアピールし、より年収の高い仕事を獲得をしたり、より自分のやりたいことのできる職場へ転職したりするのも良いでしょう!
どの業界でも生成AI導入に関しての興味関心は高まっており、AIを支えることであったりそのリテラシーがある点は高く評価されるはずです。
生成AIのトレンドと将来性
生成AI技術は、今後もさらなる進化が期待されています。
市場における生成AI技術の動向
生成AI技術は、近年急速に進化し、さまざまな分野で実用化が進んでいます。ChatGPTやGemini、Stable Diffusionといったツールは、個人だけでなく企業でも広く活用されており、業務の効率化やクリエイティブな表現の幅を広げる手段として注目されています。
市場規模も拡大しており、国内のAI市場は2027年には1兆円を超えるとの予測もあります。こうした成長に伴い、生成AIに関する知識やスキルを持つ人材の需要も高まり続けています。
必要なスキルセットとリテラシー
生成AIを活用するためには、技術的なスキルだけでなく、幅広いリテラシーが求められます。
基礎的なAIリテラシー
まず、基礎的なAIリテラシーとして、生成AIの仕組みやリスク、活用方法を理解していることが重要です。生成AIパスポート試験やGenerative AI Test(GAT) で学ぶ内容は、こうした基礎力を養ううえで有効です。
技術的なスキル
次に、技術的なスキルとして、Pythonなどのプログラミング言語や、データ分析の手法、ディープラーニングの基礎を理解していることが求められます。E資格やPython 3 エンジニア認定データ分析試験を取得することで、こうした実装力を証明できます。
生成AI資格が求められる業界の変化
生成AI資格の需要は、さまざまな業界で高まりつつあります。金融業界では、データ分析や顧客対応の自動化にAIが活用されており、製造業では、品質管理や設計業務の効率化にAIが導入されています。
また、マーケティングや広告業界では、コンテンツ制作やデータ分析にAIが活用されており、生成AIパスポート試験や文章生成AI能力検定を持つ人材が重宝されています。
まとめ!生成AI資格の選び方と取得のすすめ
本記事では生成AI資格について解説してきました。今回の結論としては、自分の目的やレベルに合った資格を選ぶことや計画的な学習を進めることが重要なポイントであり、実務に直結する考え方だといえます。
生成AI資格は、キャリアアップや業務効率化、フリーランス活動など、さまざまな場面で役立ちます。初心者向けの資格から上級者向けの資格まで幅広い選択肢があるため、自分の現在のスキルや将来の目標に合わせて選ぶことが大切です。
こうした課題を解決するために、私たち株式会社CYANdでは広告運用から戦略立案、クリエイティブ改善まで一気通貫で支援しています。実際の現場で培った知見を活かしたサービスを提供しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
2025年におすすめの生成AI資格を徹底解説!G検定・E資格・生成AIパスポートなど注目の資格をランキング形式で紹介します。試験の難易度・合格率・学習時間の目安に加え、ビジネス職からエンジニアまで目的別の選び方も詳しく解説します。